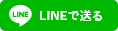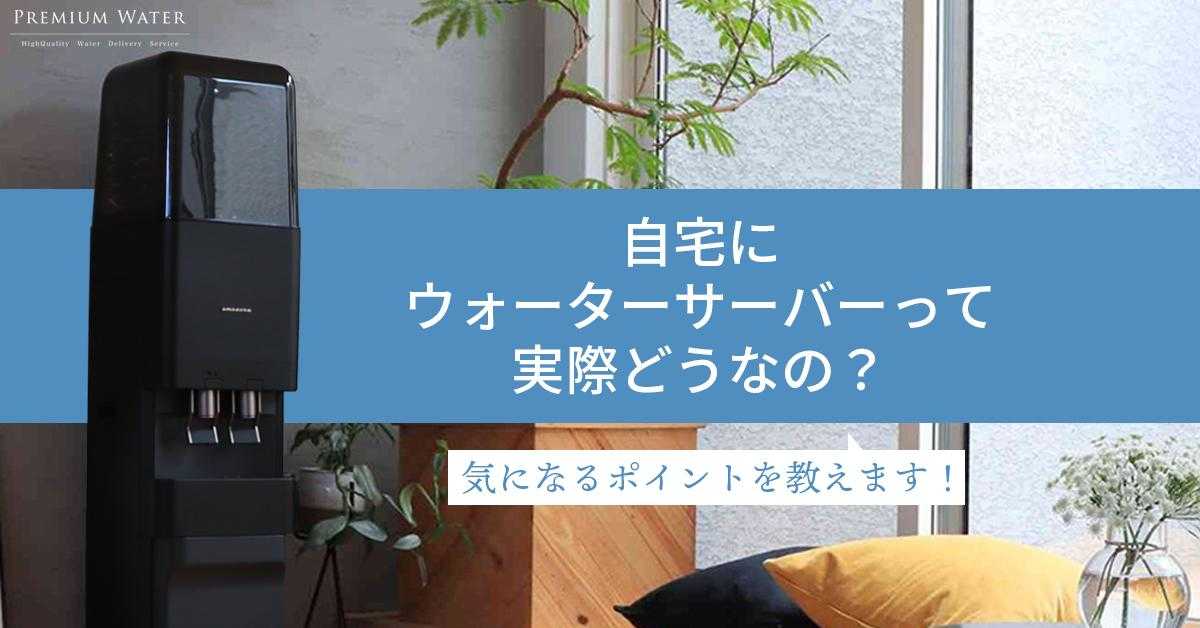水の性質や役割とは?分かりやすくカンタンに解説!

水は誰にとっても身近なものです。そのまま飲んだり、料理や洗濯に使ったり、湯船にためて入浴したりと、私たちは暮らしの中のありとあらゆるシーンで水を使っています。
生命維持や日常生活には水が必要不可欠とはいえ、「そもそも水とはどういうものなのか」「暮らしや環境にどんな影響を及ぼしているのか」と気になっている方もいるのではないでしょうか。
今回は水の性質や役割、ほかの物質との関係性等について解説します。
目次
不思議!3つの特徴がある水

水は私たちの日常生活において、水・氷・水蒸気の3つの顔を見せてくれる物質です。このような物質は水以外にありません。
普段は液体で存在している「水」は、0℃以下になると「氷」という名の個体に姿を変えます。100℃以上になると「水蒸気」と呼ばれる気体となるのは、多くの方がご存じのことでしょう。
自然界にある物質の多くは、温度が上昇すると膨張して体積が膨らみ、分子同士の密度が小さくなっていきます。 しかし水は不思議なことに、4℃(正確には3.98℃)のときに分子同士がギュッと集まって、密度がもっとも大きくなる、という不思議な性質を持っています。
水分子同士の密度は4℃を超えると再び小さくなっていき、他の物質と同様に体積が膨張します。1気圧の環境下で100℃以上になると、膨張した水分子は水蒸気となって空気中を激しく動き回るのです。※1
自然界にある物質が液体・個体・気体全ての状態(三態)に変化する様子を見るには、超高温や超低温、超高圧等の特別な条件が必要です。
例えば、塩は800℃で液体となり、1400℃で気体になることがわかっています。※2
このように水は特殊な条件でなくても、日常生活の中で三態を見られる特殊な物質なのです。
液体(水)
水分子(H2O)は1つだけでは液体にはなれません。いくつもの分子がお互いに引きあったり離れたりすることで、形を保つことのない液体という状態になっています。
液体状である水には「様々な物質を溶かしやすい」という特徴があります。空から降り注ぐ雨はもともと無味無臭ですが、空気中に漂っている成分や染み込んでいく土壌によって多種多様な成分を溶解していきます。
水がおいしいと呼ばれる地域があるのはこのためです。もちろんおいしい水がある一方で、飲み水にはふさわしくない水も存在します。
個体(氷)
水分子は4℃以下になると少し膨張し、分子同士の間に隙間ができていきます。
そして0℃以下になると、隙間がある状態で結合し、これを氷と呼びます。氷は隙間のせいで体積が大きく、水よりも比重が小さいため、水に浮くことができます。
他の物質に目を向けてみると、液体から固体になるときに体積が小さくなり、比重が大きくなる物質がほとんどです。この点でも水は特殊な性質を持っているといえます。
もし氷が浮くという性質がなければ、地球の川や湖、海に存在する氷は、水中に沈んでしまうでしょう。こうなると水位が上昇し、陸地の水没を免れられません。海や陸地は、水の性質によって保たれているという側面があるのです。※1
気体(水蒸気)
水は1気圧の環境下で100℃に達すると、水蒸気に変化して見えなくなってしまいます。お湯を沸かしたときにもくもくと白い湯気が出ますが、実は細かい水滴であって水蒸気ではありません。
水蒸気は身近な自然界にも影響を与えています。
例えば雨が降るメカニズムもその一つです。雲は地上から水蒸気を含む空気が上空に昇り、空で冷やされて生まれます。この重量が増えると雨(液体)となって地上を潤すのです。
水が気体となって蒸発するときには、周りの熱を奪う性質もあります。この気化熱によって、地表の温度や人間の体温が調節されています。※1
様々な物質と水の性質の関係って?
私たちは日常生活の中で、床や壁を水拭きしたり、衣類を洗濯したり、材料と混ぜ合わせて料理を作ったり、そのまま飲んだりと、様々な形で水を活用しています。身の回りにある物質と水の関係性について知っておきましょう。
親水性とは?
親水性とは、水となじみやすい性質のことです。一般的には「水に溶けやすい」「水と混ざりやすい」といった性質を持つものを指します。
親水性を持つ物質で身の回りのあるものといえば、お菓子づくりや料理に欠かせない「砂糖」です。砂糖はとても水に溶けやすく、水温20℃の水100mℓに約200gの砂糖を溶かすことができます。※3
お菓子や料理を作るときに何気なく混ぜている砂糖の役割は、甘みや香りをつけるだけではありません。「パンやお菓子を柔らかくしっとりさせる」「寒天をゼリー状に固める」といった働きもあり、これは全て砂糖に親水性があるからこそ実現できることです。
また、「水と人間が親しむ」という意味で「親水」という表現が使われることもあります。代表的な例が、湖や川、海等の地形を活用して整備されている親水公園です。
親水性と水溶性の違いは?
親水性とは水と物質の間に水素結合を作る性質のことで、水溶性とは物質が水によって分離され均一に広がる性質のことです。例えば食塩は水溶性が高く、食塩を溶かした水(食塩水)はどの部分も同じ味がします。
親水性があることと水に溶けることはイコールのように思われますが、決してそうではありません。
例えば「水をかけると水滴になって弾くのではなく、表面に薄い水の膜が広がる」という現象も「親水性」と表現されることがあります。水を弾かないタイプの自動車のコーティングや外壁塗装等は、その一例だといえるでしょう。水をかけると水滴となって弾くような、水となじまない性質は、「疎水性」や「撥水性」と呼ばれています。
塩素と水の性質
掃除用洗剤や洗濯用洗剤、プールの水、水道水等に含まれている塩素には、漂白作用や殺菌作用があります。
洗剤に塩素が使われるのは、黄ばみや黒ずみといった汚れを落とすためです。また、プールの水や水道水には、有害な病原菌を死滅させるために塩素が注入されています。
塩素は水に溶けやすく、水に塩素を溶かした水溶液は酸性です。
アンモニアと水の性質
独特のニオイがするアンモニアは、常温では気体の物質です。主に肥料や繊維、樹脂といった化学製品に使われていますが、日常生活でアンモニアそのものを目にすることはほとんどありません。アンモニアが原料となるもので身近なものの代表格は、ナイロンです。このほか、パーマ液や虫刺され薬にも含まれています。※4
アンモニアは水に溶けやすく、水溶液はアルカリ性です。
二酸化炭素と水の性質
二酸化炭素は空気中に0.03%ほど含まれている気体です。※5
炭素が含まれている物質を燃やすことで発生する物質で、理科の実験で二酸化炭素を発生させたことがあるという方も多いのではないでしょうか。
水に少し溶ける性質があり、水に二酸化炭素を圧入したものがシュワシュワと泡立つ炭酸水です。
水のココが面白い!

盆地が暑いのは水のせい?
周囲が山や丘に囲まれた盆地は、冬は寒く夏は暑くなる地形として知られています。
例えば京都は代表的な盆地です。ほとんど同じ緯度にある千葉と比較すると、8月の京都の平均気温は2.9℃も高く、体感だけでなく実際に気温が高いことがわかります。
この盆地の気候には、水の持つ「温まりにくく冷めにくい性質」と「気化熱が大きい性質」が関係しています。水は温度が上がると熱を蓄える性質があり、いったん熱されるとなかなか温度が下がりません。
加えて蒸発するときに熱を奪う量が大きいという特性もあります。この特性により、水が大量にある海辺や水辺のエリアでは、昼間の暑さが気化熱で和らぎます。その結果、夏と冬の寒暖差が抑えられているのです。
これに対して盆地は、水が少ないため寒暖差を和らげる気化熱が発生しません。そのため夏と冬の寒暖差、昼夜の温度差も大きくなるのです。※1
なぜ湖が凍っても湖の魚は凍らないの?
凍ると重くなる物質が多いのに対し、水は氷になると比重が軽くなって浮く、というのも特殊な性質です。このように水が氷になる性質に関して、自然界でも不思議な現象が見られます。それが「湖が凍っても湖の魚は凍らない」ことです。
寒い地域では冬に湖が凍る景色が見られます。しかし湖が丸ごと凍っているわけではありません。表面に張った氷の下では魚等の生き物が活動しています。
これは、水の密度がもっとも大きくなる温度が4℃であるためです。寒さで冷やされた湖の水は、4℃になると底へ沈んでいきます。
氷は水に浮くため、表面から少しずつ凍っていきますが、氷と湖底の間は底に行くにつれて0℃から4℃の水がある状態です。湖の底には4℃の水が維持されるため、湖底まで凍ってしまうことはありません。その結果、湖の魚たちも生きていられるのです。※2
水の役割を改めて知っておこう

地球を守っている水
水はその特殊な性質によって地球を守る役割を担っています。その1つが「水の大循環」です。そもそも地球は「水の惑星」と呼ばれるほど水が豊かな星ですが、地球上の水の約97.5%は塩水で、淡水は約2.5%しか存在しません。
しかも淡水のほとんどは南極や北極の氷として存在しています。
水の総量のうち液体として存在する淡水は、たったの約0.014%です。このわずかな水を利用して生き物は生命活動をおこなっています。生き物の生命活動が可能なのは、水が太陽に熱されて蒸発し、雲となり、雨や雪として再び地上に降りてくる循環があるからです。
この循環は「水の大循環」と呼ばれています。水の大循環には、大気の汚れを浄化する機能も備わっています。※2
水は地球の気温を保つ役割も担っています。突然ですが、地球よりも太陽に近い金星の地表温度は477℃、地球よりも遠い火星の地表温度は-47℃だとされています。これに対し、地球の表面温度は約15℃で、気温は0℃から100℃の間にあります。
この温度が保たれているのは太陽からの距離が関係し、大気中の水蒸気や二酸化炭素の存在も大きく影響しています。※3
大気中の水蒸気と二酸化炭素は、太陽の光を通し、地球の赤外線を吸収する性質があります。これが温室効果を発揮しているため、気温のバランスが取れているのです。もし大気中に水蒸気と二酸化炭素がなければ、地球の気温は約-18℃になると考えられています。※1
生命を守っている水
水は地球だけでなく生命そのものを守っています。約40億年前に海で生命体が誕生して以来、全ての生き物は水を利用して生命活動を続けてきました。水は命の源と言っても過言ではないのです。
動植物における水の存在
植物や動物にとっても水は欠かせない存在です。例を挙げると植物が水を吸い上げる力にも、水の性質が大きくかかわっています。その性質の一つが表面張力です。コップに水を満タンになるまで注ぐと、表面が盛り上がったようになる現象を見たことがある方もいるでしょう。もともと水分子にはお互いにくっつこうとする性質があり、これによって発生するのが表面張力です。
細い隙間があると、表面張力によって水は上昇していきます。植物の茎には道管と呼ばれる細いストローのような管から水が上がるようになっているのです。
植物だけでなく、動物の生命維持にも水は欠かせません。そもそも生き物の命の始まりは海であり、生き物は水から生まれ、進化して陸に上がっていったと考えられています。
このように誕生や進化の過程で、植物なら「光合成」、動物なら「代謝」という生命維持システムを、水とともに作り上げていったのです。※1
人間における水の存在
もちろん人間にとっても水は大きな存在です。人間は1日あたり約2.5Lの水分を飲み物や食べ物から摂取しています。体内の水分がたった1%失われるだけでも、のどの渇きを覚え、3%を失うと脱水症状が表れはじめます。
成人男性の場合、身体の約6割が水で占められていると考えられており、人間にとってどれほど水の存在が大きいかがわかります。
人間をはじめ生き物の体内では、水によって「代謝」という生命維持活動がおこなわれています。代謝とは、体内でエネルギーとなる物質を作り出し、不要な物質を分解する化学的な反応です。「水は様々な物質を溶かしやすい」という性質を利用し、水を溶媒として代謝はおこなわれています。※1
生命維持だけでなく、古来から人間の暮らしにも水は必要不可欠でした。今から約8,000年前に誕生したといわれる古代四大文明は、全て大河の近くで発展しています。※4
文明の発展以降も、水は暮らしに欠かせません。洗濯やトイレ等の生活用水や水力発電等、現代に生きる私たちも水に頼っています。地球はもちろん人間の生活も、水なくしては語れないのです。
限りある水を大切にしよう

蛇口をひねればいつでもお水が出てくる日本では、「お水はいつでも簡単に手に入るもの」と考えてしまいがちです。しかしお水は限りある資源であり、普段から大切に使うことを心掛けなくてはなりません。水不足や日本のお水に関する事情についても知っておきましょう。
深刻な水不足の恐れ
地球の表面の3分の2は水ですが、生き物が利用できる「淡水」はごくわずかしかありません。また、川や湖といった利用しやすい形で存在している淡水は、全体の約0.01%といわれています。※8 約79億人もの人類を含む、ありとあらゆる生き物が生存し続けていくには、この希少な水を分かち合って利用していくほかないのです。 国連事務総長が報告した「世界の淡水資源についての総括的アセスメント」によると、2025年には世界の約3分の2の人口が、水不足の状態になるのではないかと予測されています。※1 ※9 また、第2回世界水フォーラムで公表された「世界水ビジョン」においても、2025年ごろに深刻な水不足が来ると警告されました。※1 さらに2022年の第9回世界水フォーラムでは、アフリカ大陸だけに限っても4億人以上が安全な飲料水を利用できていないという報告もされています。※10
水に恵まれた日本でも大切に
四方を海に囲まれているだけでなく、年間の平均降水量が世界平均の約1.6倍もある日本は、世界から見ても水に恵まれた国です。※11
しかし実際に使える水資源は降水量の約10%と考えられており、雨が降ったとしても海に流れ出てしまう量も多く、決して無限ではありません。※12
これを機会に、日頃からお水について考え、大切にしていきましょう。
あわせて読みたい「暮らしと天然水」に関する記事
参考文献
- ※1 第1章 水の性質と役割(文部科学省)
- ※2 塩のデータ-色・融点・沸点・硬さ(公益財団人塩事業センター)
- ※3 調理に役立つ 砂糖の機能性(農林水産省)
- ※4 アンモニアが“燃料”になる?!(前編)~身近だけど実は知らないアンモニアの利用先(資源エネルギー庁)
- ※5 大気中の二酸化炭素濃度の測定(和歌山県)
- ※6 2 地球温暖化のメカニズム(環境省)
- ※7 環境白書 2 古代文明からの教訓(環境省)
- ※8 世界の水資源(国土交通省)
- ※9 世界人口白書2022(UNFPA Tokyo)
- ※10 アフリカの水と衛生分野の進捗に警鐘 4億人以上が安全な飲料水を利用できず(ユニセフ)
- ※11 日本の水資源の現況(国土交通省)
- ※12 日本の水収支(国土交通省)
シェアNo.1の天然水ウォーターサーバーは「プレミアムウォーター」
豊富なデザインで業界シェアNo.1のプレミアムウォーターでは、非加熱のこだわりの天然水をご自宅にお届けいたします。