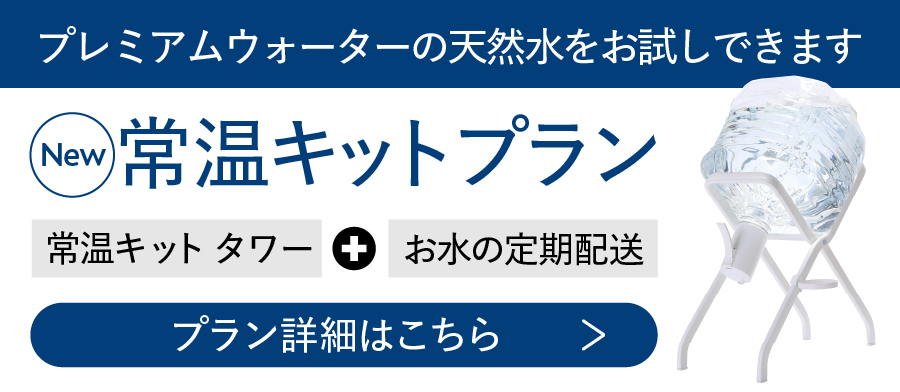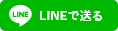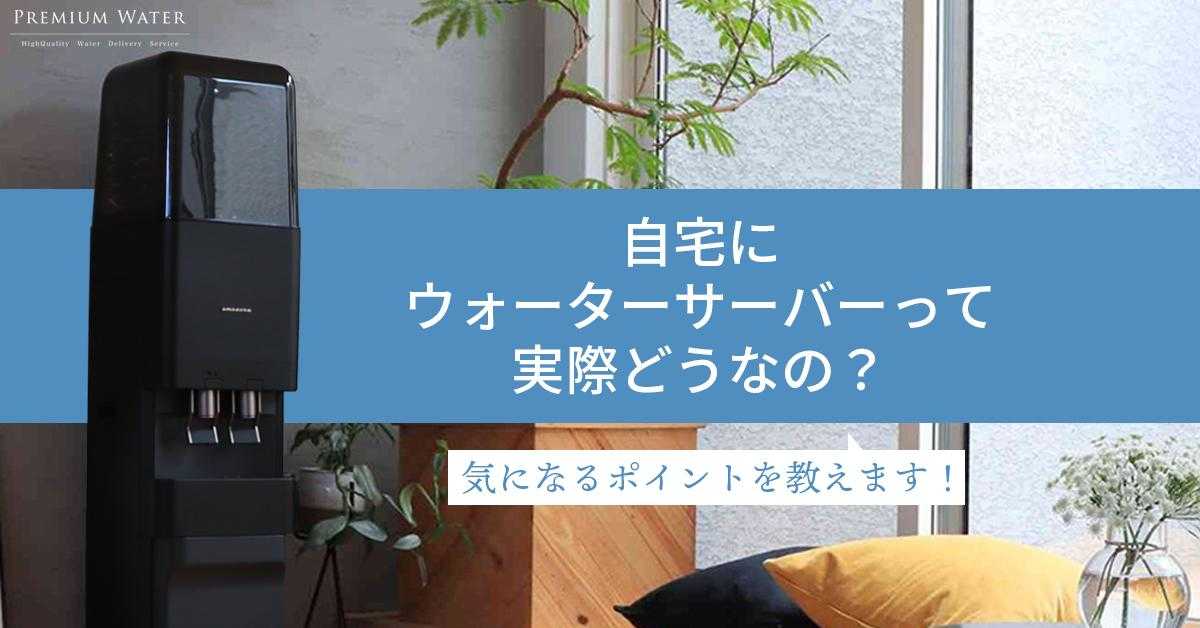津波防災の日とは?11月5日に制定された由来を解説

地震の後に発生する津波は、瞬く間に命を脅かし、また繰り返し襲ってくる非常に危険な災害のひとつです。11月5日の「津波防災の日」は、その脅威を思い出し、正しい知識と避難行動を家族で確認するための日として定められました。
日本では、東日本大震災や能登半島地震等で大きな地震が起こり、甚大な被害をもたらしています。防災に対する意識を高めるため、家族全員で「津波防災の日」についての知識を身につけましょう。
▼この記事のポイント
11月5日「津波防災の日」の由来や目的、津波の危険性から身を守るための避難知識、家庭でできる備えについて解説しています。
津波防災の日(11月5日)とは
【由来】
1854年の安政南海地震で、濱口梧陵が稲わらに火を放って(稲むらの火)村人を高台へ誘導し、津波から救った逸話にちなみます。2011年の東日本大震災の教訓を受け、津波対策の推進に関する法律で制定されました。
【目的】
津波に関する正しい知識と、迅速かつ適切な避難行動を身に付け、被害を軽減することを目的としています。2015年には国連総会で「世界津波の日」としても制定されました。
災害への備えと対策
- 避難行動:津波警報等が出た際は「まず避難」が原則です。ハザードマップで避難場所や高台を確認し、家族と集合場所や連絡手段を共有しておくことが重要です。
- 備蓄の重要性:ライフライン停止や物流の混乱に備え、最低3日~1週間分の食料と飲料水(1人1日3L)の備蓄が推奨されます。
- ローリングストック:普段の食品やお水を多めに買い置きし、消費しながら買い足す方法で、無理なく備蓄を継続できます。
プレミアムウォーターの活用
ウォーターサーバーのボトル(1セット24L)をストックしておけば、自然と必要な備蓄量を確保できます。停電時でも使用可能なウォーターサーバーや非常用キットを活用すれば、災害時も安心です。
目次
なぜ11月5日が「津波防災の日」?「稲むらの火」に込められた教訓とは

まずは「津波防災の日」の成り立ちと目的を知り、家庭や地域で津波に備えるきっかけにしましょう。
「津波防災の日」の由来と目的
2011年の東日本大震災では、津波の脅威そのものや、逃げ方・判断の仕方を知らなかったことが被害拡大の一因となりました。
この教訓を受け、津波被害の軽減を目指す法律が整備されたのが2011年6月です。ここで、津波に関する観測体制の強化や調査・研究の推進等が定められました。
この中で制定された日が、11月5日の「津波防災の日」です。逸話「稲むらの火」にちなんで制定されており、津波に関する正しい知識や適切な避難行動を国民が身につけることを目的としています。
津波防災の日には、全国各地で住民参加型の防災訓練や公開討論会、シンポジウム等が実施されています。このように継続的に訓練し、様々な取組みをおこなうことで、人々の防災意識が高まり、万が一の際もより多くの命を守ることにつながります。※1
稲むらの火とは?
前述したとおり、津波防災の日は「稲むらの火」という逸話にちなみ、11月5日に制定されました。
11月5日という日付は、安政元年11月5日(太陽暦で1854年12月24日)に起きた安政南海地震により、津波が紀州藩広村(現在の和歌山県)を襲ったという出来事に由来します。
このとき、庄屋であった濱口梧陵は津波の危険に気づくと、収穫した稲わらの山(=稲むら)に敢えて火を放ち、村人たちに「高台へ逃げよ」という合図を送りました。火に気づいた人々は高台へ避難し、結果として多くの命が救われたのです。※1
この教訓を後世に伝える逸話が「稲むらの火」です。
「稲むらの火」のあらすじ
高台に住む庄屋の五兵衛は長くゆったりとした地震の後、家から出て村を見下ろした。しかし、村人は豊年を祝う祭りの準備で地震には気付いていない様子だ。五兵衛が目を海にやると、潮が引き、広い砂原や岩底が現れている。
津波がやって来るに違いないと直感した五兵衛は、自分の畑に積んであった取り入れたばかりの稲むらに次々と松明で火を放った。すると、火に気付いた村人が火を消そうと高台に次々と駆けつけた。村人が五兵衛のもとに集まってしばらくすると、津波が村を襲い、村は跡形もなくなってしまう。その様子を見た村人は、五兵衛が稲むらに放った火によって命が救われたことに気付くのであった。
引用 特集 津波防災の日(内閣府)
この物語は昭和の国語読本や現代の国語の教科書にも掲載されています。
また、2004年のスマトラ沖地震を受け、英語やタイ語等の9か国語で「稲むらの火」を掲載した津波防災の教材が作られました。※1
このように「稲むらの火」の教訓は、後世の私たちに伝わるだけでなく、世界にも広がっています。
いろいろある「防災の日」

防災関連の日は、「津波防災の日」以外もあります。名称や日付、目的が少しずつ異なるため、ここで代表的な日を知り、理解を深めましょう。
防災の日(9月1日)
1923年(大正12年)9月1日の関東大震災を由来として制定された日です。関東大震災は、死者・行方不明者が10万5千人以上の大災害でした。
「防災の日」の目的は、関東大震災にちなみ災害への認識を深め、家庭や地域での備えを充実・強化することです。毎年9月1日を含む1週間(8月30日〜9月5日)は「防災週間」とされており、全国で様々な訓練や啓発イベントがおこなわれています。※2
津波防災の日(11月5日)
前述のとおり、安政南海地震の逸話「稲むらの火」にちなんで制定された日です。津波災害の被害軽減を目的に、正しい知識の普及と迅速な避難行動の定着を図る日となっています。
防災とボランティアの日(1月17日)
1995年1月17日の阪神・淡路大震災の際に、被災地の救援・復旧へ多くのボランティアが参画したことを踏まえて制定されました。
目的は、ボランティア活動の重要性と自主的な防災活動への参加意識を深めることです。毎年1月15日〜21日は「防災とボランティア週間」とされており、この期間に防災やボランティアに関する様々な関連行事がおこなわれています。※3
世界津波の日(11月5日)
2011年に発生した東日本大震災の教訓をもとに制定された「津波防災の日」。この日本の取組みと、津波防災の意識を世界で共有する重要性を受け、日本をはじめとする142か国が共に提案したものが、2015年の国連総会で満場一致で採択されました。
これにより、日本の「津波防災の日」と同じ11月5日が国際デーとなり、世界中で津波のリスクに関する意識を向上させ、津波対策を強化する重要な日となっています。※4
目的は、世界中で津波のリスクに関する意識を向上させ、津波対策を強化することです。この日をきっかけとし、各国で津波被害の対策がおこなわれ、復興が推進されることが期待されています。
いざという時のために災害対策をしておこう

津波をはじめとした災害は、ある日突然やってきます。
被害を最小化するポイントは、日頃の準備と家族との情報共有です。備蓄を整え、避難先や連絡手段を確認し、いざという時に迷わず動ける体制を今から作っておきましょう。
避難準備と家族との情報共有
地震や津波の際は、電気・ガス・水道・通信等ライフラインが止まる可能性があるため、備えが欠かせません。食料等を備蓄しておき、ライフラインが止まってもある程度、生活できる体制を整えましょう。
また、危険区域にいるときは「まず避難」が原則です。指定避難所や親戚・知人宅も候補にして、家族で集合場所と連絡手段を決めておきましょう。非常用持ち出し品はリュックにまとめ、玄関等持ち出しやすい場所へ置いておくと安心です。※5
加えて、自治体のWebサイトや国土交通省のハザードマップポータルサイトをチェックし、防災マップやハザードマップを入手しておきましょう。自宅や職場のリスク、避難経路、高台等を事前に確認し家族と話し合っておくと、慌てず行動できます。
- ハザードマップポータルサイト(国土交通省)
食品の備蓄が大切
災害時はライフラインが止まるだけでなく、道路寸断や停電により物流が滞り、店舗に商品が並ばないことがあります。過去の災害でも復旧までに1週間以上を要した事例が多く、支援物資がすぐに届かない可能性も想定しなければなりません。
備蓄量の目安:
ご家庭では、最低3日間~1週間分×人数分の食品の備蓄が必要です。特にお水は生命線です。飲用・調理用・衛生用を含め、1人1日3L程度を基準に備蓄しましょう。※5
ローリングストック:
食品は主食、たんぱく源、野菜・果物、おやつや経口補水液等の常温保存品を中心に準備。普段から少し多めに買い置きし、古いものから順番に消費してその分を買い足す「ローリングストック」という方法なら、効率良く備蓄できます。※6
災害に備え事前に備蓄を

津波防災の日は、東日本大震災の教訓を受け「稲むらの火」にちなみ11月5日に制定された日です。災害は突然やってきますが、日頃の備えがあれば、被害を最小限に抑えることができます。飲用水は1人あたり1日3Lの計算で、1週間分計21Lを準備しておくと安心できます。
プレミアムウォーターなら、1セット(12L×2本)をストックするだけで、自然に必要量の確保が可能です。停電時に使える手動レバー式ウォーターサーバーや非常用キットも用意されており、電気が止まってもお水が飲めて、調理やうがいにも活用できます。
万が一に備え、ローリングストックで自然とお水の備蓄ができる、プレミアムウォーターのウォーターサーバーを導入してみてはいかがでしょうか。
あわせて読みたい「暮らしと天然水」に関する記事
参考文献
- ※1 特集 津波防災の日(内閣府)
- ※2 防災の日(政府広報オンライン)
- ※3 防災とボランティアの日(政府広報オンライン)
- ※4 世界津波の日(内閣府)
- ※5 災害時に命を守る一人ひとりの防災対策(内閣府)
- ※6 今日からできる食品備蓄。ローリングストックの始め方(政府広報オンライン)
シェアNo.1の天然水ウォーターサーバーは「プレミアムウォーター」
豊富なデザインで業界シェアNo.1のプレミアムウォーターでは、非加熱のこだわりの天然水をご自宅にお届けいたします。